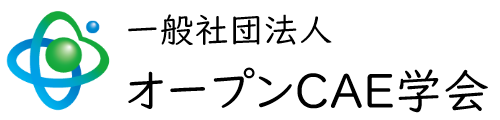トレーニング
- オープンCAEに関するトレーニングを開催します.
日時
- 2025年12月11日(木)
場所
- シンポジウム会場: 足利商工会議所友愛会館(〒326-8502 栃木県足利市通3丁目2757)
- 会議室での対面式トレーニングを基本とし,希望者にはオンラインでの受講も可能なハイブリッド開催となります.オンラインではタイムリーなサポートが困難なことから,質問時間での回答など必要最低限のサポートのみになります.講習概要を確認し,サポートが必要と思われる方は現地参加をご検討ください.
タイムテーブル
| 時間 | トレーニングA(A室) | トレーニングB(B室) | トレーニングC(C室) |
| 10:30 - 11:00 | 受付 | - | - |
| 11:00 - 12:30 | A1:OpenFOAM講習(入門)-OpenFOAMによる熱流体シミュレーション入門 講師: 中川慎二 (富山県立大学) | (午前はAコースのみ実施) | (午前はAコースのみ実施) |
| 12:30 - 13:30 | 休憩 | 休憩 | 休憩 |
| 13:30 - 15:00 | A2:OpenFOAM講習(初級)-OpenFOAMによる熱流体シミュレーション初級 講師: 中川慎二 (富山県立大学) | B2:AIを利用したOpenFOAMの速習法 講師: 川畑真一 (オープンCAE勉強会@関西) | C2:PrePoMaxによる3D非定常熱伝導解析 講師: 小南秀彰 |
| 15:00 - 15:10 | 休憩 | 休憩 | 休憩 |
| 15:10 - 17:10 | A3:日本機械学会流体工学部門連携トレーニング:データ科学入門 - OpenFOAMおよびPythonを用いたモード解析 講師: 池田拓士, 上林 出 (荏原製作所) | B3:Gmsh入門 講師: 田村守淑 (オープン科学計算コンサルティング) | C3:OpenModelicaによる熱流体システムモデリング 講師:zeta_plusplus(Modelica勉強会) |
講習内容
本トレーニングの講習内容をご紹介します。
- A1:OpenFOAM講習(入門):OpenFOAMによる熱流体シミュレーション入門
- 講師:中川 慎二 (富山県立大学)
- 講習概要:密閉容器内の自然対流を例にとり,OpenFOAMを使ってソルバの選択から結果の可視化までの一連の流れを体験します.本コースに合わせて,引き続き初級コースを受講することで,日本機械学会計算力学技術者熱流体分野初級認定申請資格・2級受験資格が得られます.参加者の用意したPC上で講習用仮想マシンのOpenFOAMを操作します.
- 事前準備: OpenFOAM-v2406と講習用例題などを含んだ仮想マシン・アプライアンスを配布します.参加登録完了後に参加者向けに事前にお知らせするリンク先から仮想アプライアンス (OVAファイル) を入手し,仮想環境Virtualboxなどへインポートしてください.これにより,講習会用仮想マシンが起動できることをご確認ください.参加登録前の動作確認用の仮想マシン・アプライアンス(資料・一部環境など含まないもので,実習本番用ではありません。)は,こちらから取得できます.
A2:OpenFOAM講習(初級):OpenFOAMによる熱流体シミュレーション初級
- 講師:中川 慎二 (富山県立大学)
- 講習概要:入門コースを受講された方を対象に,密閉容器内自然対流の例題を使って,実験結果との比較により妥当性を検討しながら,メッシュや境界条件への依存性について学びます. 入門コースと合せて受講することで、日本機械学会計算力学技術者熱流体分野初級認定申請資格・2級受験資格が得られます.
- 事前準備: A1と同じ環境を利用します.
A3:日本機械学会流体工学部門連携トレーニング:データ科学入門 - OpenFOAMおよびPythonを用いたモード解析
- 講師:池田拓士, 上林 出 (荏原製作所)
- 講習概要:OpenFOAMによって円柱回りのカルマン渦を計算し、Pythonによるモード解析により支配的なモードを抽出を行います。本講習によって、流体工学におけるデータ科学の応用事例を体験し、ある流体現象の支配的な現象を抽出する一連の技術を習得できます.
- A1と同じ環境を利用します. PCはご自身で準備頂き, 仮想マシンのインストールと動作確認を事前にお願いいたします.
B2:AIを利用したOpenFOAMの速習法
- 講師:川畑 真一(オープンCAE勉強会@関西)
- 講習概要:どこから勉強したらいいのかわからない, 勉強する時間がなかなか取れない人向けにAIを活用して,急いでOpenFOAMの勉強を進めていく方法の一例を示します.OpenFOAM入門, 初級編の学習済でOpenFOAMの基本動作は理解している人向けです.
- 事前準備:講習資料に事前準備を記載しております。必須ではございませんので、講習会中に同じ操作をされたい方のみご準備ください。ネット環境はご用意ください。
B3:Gmsh入門
- 講師:田村守淑 (オープン科学計算コンサルティング)
- 講習概要:Gmshはフリーのメッシュジェネレータです.メッシュだけでなく、形状作成やポスト処理などもできます.GmshのGUIは多様な機能がありますが、使い方の情報があまりありません.今回、人が実際に使っているのを見ると理解が深まると考え, GUIの使い方の実演, トレーニングを行います. Gmshの概要,画面,メニューの説明の後, 基本的な梁とフランジのメッシュ作成の実習を行います.
- 準備:Gmsh サイトから計算環境に応じて、安定なバイナリーファイルをダウンロードし解凍して準備してください.
Windows: gmsh-4.14.1-Windows64.zip
Linux: gmsh-4.14.1-Linux64.tgz
Mac: gmsh-4.14.1-MacOS.dmg
A1-A3の流体コース向けの仮想マシンにも, Linux版のファイルをダウンロードしてあります. そちらを使って受講することも可能です.
C2:PrePoMaxによる3D非定常熱伝導解析
-
- 講師:小南秀彰
- 講習概要:はじめて熱伝導解析を行う受講者を想定し,PrePoMaxの操作を体験します.伝熱工学の基礎知識とPrePoMaxの入力パネルの関係を説明しながら,単一材料と複合材料それぞれのモデルで定常伝熱と非定常伝熱の解析操作をします.PrePoMaxの内蔵CAEソルバーCalculiXにあるBeam要素(1D要素)とSolid要素(3D要素)の違いについても説明します.
- 事前準備:講習会ではPrePoMax ver2.3.0を利用します. 各自PCにPrePoMax ver2.3.0のインストールを済ませておいてください.詳細はオープンCAEWiki PrePoMaxのインストールを確認ください.なおPrePoMaxのダウンロードサイトはこちらです.
C3:OpenModelicaによる熱流体システムモデリング
- 講師:zeta_plusplus (Modelica勉強会)
- 講習概要:OpenModelicaのModelica Standard Library中でFluidライブラリを用いた流体システムのモデリング解析を行います.Modelica Standard Libraryを用いた,ハンズオン入門的な例題1つ実施し,外部の3rdParty libraryの読込方法と,それを用いた例題1つ実施する予定です.
- 事前準備:OpenModelica Ver.1.25.5 を用いる予定です(1.25下のバージョンアップが頻繁ですが、bug fixリリースのようで大きな変更は為されていないので, 1.25以降であれば問題ないです). 事前に各自PCへインストールをお願いします. インストールの方法詳細については, 以下を参考にしてください.
OpenModelicaのインストール(講師zetaplusplusさんのHP)
OpenModelicaインストール(バージョン古いが、Windows以外の環境にインストールする場合はこちらを参考にしてください) また念のため以下 github に上がっているの例題も事前に各自のPCダウンロードしておいていただけると当日スムーズに実施できます 当日使用予定例題